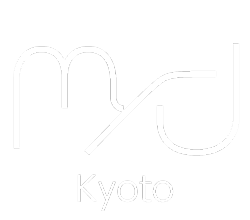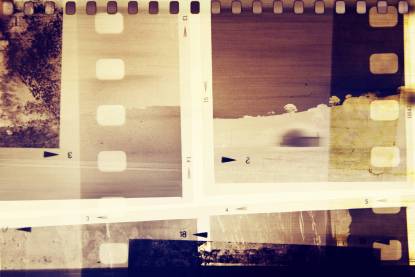第一回「初めに」
この度、このコーナーで京都のことについて書くことになりました辻井と申します。
よろしくお願いします。
まず、自己紹介をさせていただくと、私は京都生まれで京都育ち、現在は京都の観光ガイドをしております。私が他の京都観光ガイドの方に対してアドバンテージがあるとするなら、江戸時代から同じ土地の上に暮らしてきた生粋の京都人家系であるということでしょうか(家は建て直されていますが)。京都の香りや雰囲気を、特に京都以外の方にお伝えできればと考えています。
井上章一さんは「京都ぎらい」という本の中で、嵯峨(洛外)生まれの井上さんが洛中生まれの人から蔑まれたという事を書いておられますが、私はその洛中の出身になります。
他の地域の方から「京都は第二次大戦で空襲の被害をほとんど受けなかったので、羨ましい。」とよく言われます。
しかし、実は京都は原爆投下候補地の第一候補地でした。昭和6年(1931年)にヘンリー・スティムソンというアメリカ人が夫婦で京都観光をしています。この人は9年後、アメリカの陸軍長官になり、さらに5年後、1945年日本に原爆投下を決定する委員会の委員長になりました。
ヘンリー・スティムソンは1人、京都に原爆を落とす事に猛反対します。そして、トルーマン大統領に2回直訴して京都を投下候補地から外させました。その結果、第二投下候補地の広島に原爆が落とされることになりました。
「バタフライ効果」というのがあるのをご存知でしょうか?「北京で蝶が羽ばたくと、ニューヨークで暴風雨になる」という例えです。「そんなアホな!」と思われるかもしれませんが、スーパーコンピューターで1か月後の気象予測をした時に、蝶の羽ばたきのようなごくわずかな気流の乱れをデータに加えるだけで晴天だった予測が暴風雨に変わってしまうことがあるそうです。
何年か前に放送された、村上もとかさん原作、大沢たかおさん、綾瀬はるかさん、中谷美紀さんが出演していたドラマ「仁」のなかでも「バタフライ効果」が出ていました。その他、マイケル・J・フォックスやクリストファー・ロイドが出演していた「バック・トゥ・ザ・フューチャー」という映画のシリーズも、おそらくは「バタフライ効果」がテーマだと思います。
もし、1組のアメリカ人夫婦が京都観光をしていなければ、何十万人の日本人の運命が変わった可能性があります。原爆投下予定地点は現在の梅小路公園・鉄道博物館の蒸気機関車の方向を変える転車台でした。京都の中心に近く、爆撃機(B29)から目標としやすいという理由です。私の実家もそんなに離れていないので、京都に原爆が落ちていれば、この原稿を入力している私は存在していません。
その他、「モニュメンツメン」という人達もいました。アメリカが戦争に勝っても、人類の文化遺産を空襲して破壊してしまうと戦後に世界から非難を受けるという事で、ラングドン・ウォーナー(日本美術の専門家)という人が中心になって、「京都・奈良・鎌倉・東京の私設美術館」などの空襲を避けるように指示したといいます。
結果として、京都は原爆やほとんどの空襲の被害を免れました。また、東大寺や鎌倉の大仏も現在まで残ることになります。
私の亡くなった祖父や母からは「京都は文化財が多かったから、空襲できなかった。」と子供の頃、聞かされました。それが、当時の京都人の考えでした。第二次大戦中、祇園甲部歌舞練場などでは極秘に「風船爆弾(世界最初の気象兵器といわれます)」を作っていて、京都は空襲されないという安心感があったようです。
この地球に生命誕生の条件が奇跡的に揃い、人類が生まれ、進化し、たくさんの飢餓や戦いをくぐり抜け、現在の私たちが存在しています。そんな事を考えると、つまらないことやささいなことで、腹をたてるようなこともなくなる気がします。明石家さんまさんの言われる「生きてるだけで丸儲け」でしょうか。
京都本を書いておられる方は実は京都以外のご出身の方が多いようです。京都人は京都の文物、風習に何の違和感もなく、暮らしていますが、他の地域の方こそがその違いを発見できるのでしょうか。儀式作法研究家の先生が以前、「京都人は水無月(和菓子)というお菓子は全国で売っているように思っている(実際は京都と京都周辺のみ)。」と言われていました。
これから、私の視点で京都の事を書いてみたいと思います。面白い情報になるかどうかは分かりません。独りよがりの情報になるかも知れません。その時には、どうぞ遠慮なく御指摘いただくようにお願いします。
辻井 輝幸
最新記事 by 辻井 輝幸 (全て見る)
- 「京都一周トレイルのススメ」詳しすぎる、辻井輝幸の京都随想記 - 2018年8月22日
- 「夏の風物詩、大文字送り火」詳しすぎる、辻井輝幸の京都随想記 - 2018年8月8日
- 「今だから話せるちょっと野暮な体験談2」詳しすぎる、辻井輝幸の京都随想記 - 2018年7月18日