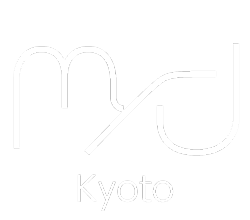第八回 わらべ歌「まるたけえびすに…」の秘密
皆さんは「まるたけえびす」から始まる京都のわらべ歌をご存知ですか?京都ではよく知られたわらべ歌です。
「まるたけえびすに……」の中で「まる」は「丸太町通」を意味し、「たけ」は「竹屋町通」、「えびす」は「夷川通」、「に」は「二条通」というように京都の町の東西の通り名を歌って憶えるというものです。
一般には、京都の親が子供に、このわらべ歌で通り名を憶えさせるとネットや本では説明されています。
でも、私の母は違う考えを持っていました。
「京都生まれの子なら、すぐに通り名くらい憶えられるし。
この歌は地方出身の丁稚さんのための歌やわ。」と言っていました。
昔は長子相続制でした。
つまり、長男(たいていの場合、長子には長女は含まれませんでした)が、すべての家督・財産を相続するという制度でした。
井沢元彦さんの「逆説の日本史」でしたか?「ずっと以前の鎌倉時代くらいまで(記憶違いならゴメンナサイ)均等に兄弟に分けられていたが、代が進むと田畑が小分けになり、食べていけなくなって長子相続という制度になった。」と書いてあったと思います。
田畑を分けるのは愚かな事として「田分け(たわけ:戯け)」という言葉が生まれたとか。
織田信長は家の中に居場所がない農家の次男以降の男たちを集めて親衛隊をつくり、また傭兵としての軍を作りました。
傭兵ですから実家とは切り離されています。ということは、負け戦になると逃亡する可能性が他国の兵より高いといえます(他国の兵だと逃亡すると実家がひどい目にあわされました)。
確か、司馬遼太郎さんの「国盗り物語」では、「信長の偉さは最初に世に出たのは『(奇襲の)桶狭間の戦い』だが、信長は二度とリスクの高い奇襲を使わなかった。
人間は一度うまくいくと、また同じ手を使いたくなるものだが・・・。」というような意味の事が書いてありました。
家の縛りが他国の兵より弱い信長軍は、負けるわけにいかないんですよね。
『桶狭間の戦い』の以降はいろいろな所と同盟を結び、常に相手よりも多い戦力で負けない戦(いくさ)を心掛けていました。軍を傭兵化することにより、他国の兵のように田植えや稲刈りの時に国元に帰らなくてもよくなって、一年中、戦ができる様になったのです。
話が脱線してしまいました。
江戸時代になると、次男以降の男の子は口減らしにお寺に預けられるか、京や大坂の商家に丁稚奉公に出されるのが多かったようです。
そして、真面目に勤め上げて、のれん分けをしてもらうのを目指すか、番頭として店の管理職として残るのか、あるいは、その商家に男の跡継ぎがいなければ、婿養子や養子としてその商家を継ぐこともあったでしょう。
では、女の子の場合はどうでしょうか?お年頃になると、嫁に行くことになるのですが、家が貧しい農家だと口減らしに、やはり京や大坂の商家に7・8歳くらいで、子守として奉公に行かされました。
子守の辛さを唄ったのが、京都のわらべ歌「竹田の子守唄」です(40数年前、赤い鳥というフォークグループがヒットさせました)。
盆と正月は親元に帰ることが許されることが多かったと思いますが、「自分が帰ることで幼い弟や妹の食べる分が減ってしまうんじゃないか。」とか、また「親に食べ物の余計な苦労を掛けてしまう。」と気遣うような子供たちでした(母から聞いた話ですけれど)。
行願寺(革堂)には悲しい話が残っています。それは幽霊の描かれた絵馬が奉納されているのです(「幽霊絵馬」といいます)。
江戸時代の終わり頃、革堂の近くの質屋で子守りの奉公をしていた「おふみ」という女の子がいました。
革堂から聞こえてくる御詠歌を子守歌がわりにしていました(革堂は天台宗です)。
でも、奉公先の主人の八左衛門は熱心な法華信者で、「おふみ」が御詠歌を子供に教えているのを見て、怒りに狂って「おふみ」を殺してしまいます。
そして、庭に埋めて「おふみ」の両親には男と失踪したしたとウソをつきました。
両親が革堂に泊まった時に「おふみ」の幽霊が現れて「主人に殺され庭に埋められています。」と告げました。
両親はこのことを奉行所に伝え、質屋の主人は捕まることになります。
両親は「おふみ」の姿を絵馬に描き、革堂に奉納したのが「幽霊絵馬」です。
「幽霊絵馬」は8月22~24日頃(年によって違う事があるようです)に一般に公開されます。
絵の具が大分、剥離してきていますが、まだ十分に判別できました。
本当に「おふみ」の幽霊が出たのかどうかは分かりません。
でも、そんな悲しい話が生まれるほど、当時の子供たちは過酷な状況に置かれていました。
長く歌い継がれたわらべ歌には人々の(子供たちの)想いが込められています。
時には、そんなことも考えてみて下さい(実は、母には悪いのですが子供の頃、京都育ちの私も通り名を「まるたけえびすに・・・」で憶えました)。
辻井 輝幸
最新記事 by 辻井 輝幸 (全て見る)
- 「京都一周トレイルのススメ」詳しすぎる、辻井輝幸の京都随想記 - 2018年8月22日
- 「夏の風物詩、大文字送り火」詳しすぎる、辻井輝幸の京都随想記 - 2018年8月8日
- 「今だから話せるちょっと野暮な体験談2」詳しすぎる、辻井輝幸の京都随想記 - 2018年7月18日