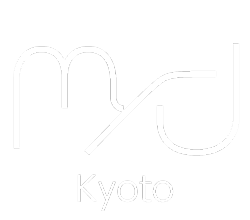第十一回「元祖二刀流の宮本武蔵について」
今年はメジャーリーグ・エンジェルスの大谷翔平選手の二刀流が話題ですよね。
それで、元祖二刀流の「宮本武蔵」を取り上げようと思います。
宮本武蔵の「二刀流」は正式には「二天一流」というのでしょうけど、ここでは一般的に呼ばれている「二刀流」で統一しておきます。
京都には宮本武蔵ゆかりの場所がいくつかあります。
「吉岡一門との決闘」が有名で、一乗寺下がり松・八大神社・三十三間堂・東寺の観智院などの場所があげられます。東寺の観智院には宮本武蔵が描いた鷲や竹林の水墨画が残っています(長谷川等伯に絵を習っていたとか)。
「吉岡一門との決闘」の後、観智院にかくまわれていたといいます。
観智院の絵から「筆の使い方から左利きであることが分かる」という人がいます。
でも、どうなんでしょうか?筆で文字を書く時には左利きは結構、難しいと思います(撥ねる時など)。
しかし、絵を描く時には左手を使った可能性があります。
「二刀流」を極めるため、左右を使えるように練習したかもしれません。
ちょうど、メジャーリーガーのダルビッシュ投手が、右利きであるのにも拘らず、体のバランスを保つため、左手でサインボールを投げたりします。
武蔵が左利きだとしたら、「二刀流」の発想をしたのには納得いくんですよね。
実は私も左利きです(文字を書く時は右手を使いますが)。
日常生活で使うものは右利き用に出来ている物が多く、左利きの人間はごく自然に、小さい頃から右手も使えるようになりますし、私も子供の時から左右の握力はほとんど同じでした。
「左右の手が同じように使えるなら、両方の手に刀を持てばいいじゃないか」と思っても不思議じゃないですよね。
「武蔵が左利きならなぜ、刀を左の腰に差していたんだ。」と反論する人はおそらく、右利きの人なんでしょう。
昔、クリス・エバート、ジミー・コナーズなどのテニスの両手打ち(バックハンド)の選手のプレーをテレビで見て(1970代後半くらいでしょうか?)気付きました。
両手打ちだと片手打ちに比べてラケットが遠くまで届きません(両手打ちは、よりフットワークが必要になります)。
そうです、宮本武蔵の二刀流というのは2本の刀を持っていることに意味があるだけでなく、片手で刀を持つことにも大きな意味があるんですね。
同じ刀の長さであっても、両手で刀を持つより、片手で持った方がより遠くまで、切っ先が届くことになります。
西洋のフェンシングはこの考え方でしょうか。
それに加えて、片手で刀を持つ利点がもうひとつあります。
それは構えた時や攻撃時に体が半身(はんみ)になるということです。
半身(体が相手に対して斜めになります)になると、相手から見て、前面投影面積が正対する場合に比べて小さくなるので、相手の攻撃を胴体に受けるリスクを減らせます。
確か、前面投影面積を極力、減らして被弾リスクを軽減したアメリカ陸軍の対戦車ヘリコプターがあったと思います。
相手との距離がある時には、長刀を使い、接近戦になった時には小刀(しょうとう)を。
また、長刀で相手の長刀の動きを封じて、小刀で突くという方法が考えられます。
いいことずくめのようですが、二刀流の欠点を考えると片手で刀を持つために体力が必要になります。
特に、上段の構えはキツイかもしれませんね。銅像や映画・ドラマでは両手の刀を横からやや下に構えているポーズが多いようです。上段の構えが使えないのはつらい。
上から刀を振り下ろすなら、重力を利用できるのでスイングスピード(?)を速くできるのですが、水平よりも下の位置の構えだと長刀は突きと相手の刀を受けるために使ったと考える方が自然のような気が・・・。
それに人間の目は上下の動きを見るのを苦手にしているとか。
きっと、原始時代の我々の祖先たちがイノシシやウサギを狩る時に動物の左右の動きを目で追う必要があって、横方向の動体視力が発達したのでしょうけど。
空手に「かかと落とし」という技があります。
昔、K1の格闘家アンディ・フグ選手が得意にしていた技です。脚を上げて、振り下ろすのですが(垂直方向の動きの技)、これが結構決まるみたいです。
そこで、思いつきました。スロットマシンというのは上下に数字や絵が動きますね。
絵などを三つ揃えて止めればOKのゲームです。それならば、首を90°横にして上下の動きを左右の動きに変えて見れば、動きについていけるのではないかと・・・(そんなアホな?)。
誰か、ギャンブル好きの方、試してみる気はありませんか?
また、話が脱線してしまいました。スミマセン。冒頭で書きました一乗寺下がり松・八大神社・三十三間堂・東寺の観智院の事はネットでお調べください。
武蔵の絵の先生ともいわれる長谷川等伯の国宝の「楓図」は三十三間堂近くの智積院にあります。
宮本武蔵の足跡を辿る京都観光というのはどうでしょうか?
辻井 輝幸
最新記事 by 辻井 輝幸 (全て見る)
- 「京都一周トレイルのススメ」詳しすぎる、辻井輝幸の京都随想記 - 2018年8月22日
- 「夏の風物詩、大文字送り火」詳しすぎる、辻井輝幸の京都随想記 - 2018年8月8日
- 「今だから話せるちょっと野暮な体験談2」詳しすぎる、辻井輝幸の京都随想記 - 2018年7月18日