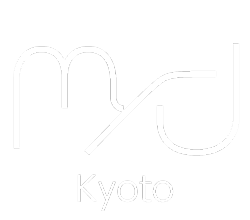本と読書。
世の中には、読書を目的とした旅をする人たちがいる。
どこかで、本を読む。その為だけに、見知らぬ土地を訪れる。
本を携えて。

京阪電車に乗って、出町柳駅で下車する。そこから、目の前に見える橋を渡って少し歩けば、京都・出町桝形商店街に着く。
かつて、わたしはこの町に住んでいた。
いま、この商店街には、できたてほやほやの映画館や本屋が立ち並んでいる。
今のほうが、ずっと活気があって、まだ見たことのない希望とサプライズの予感に溢れている。
新しく出来たばかりの出町座を訪れた。ここには、映画館と書店(CAVA BOOKS)とカフェ(出町座のソコ)が併設されている。
一階にある書店で「絶望図書館」というタイトルの短編集を購入してから、カフェでオムレツサンドを注文した。
旅の醍醐味は、本の現地調達と、地元だけの料理だ。
しばらく待っていると、聞き覚えのある声が飛んできた。
「久しぶりだね、らぶてあさん」
友人のTさんが、オムレツサンドを手にして、にっこりと微笑んでいた。
彼女は、このカフェの店長を務めていた。
わたしたちは、互いの近況報告を済ませてから、たわいもないお喋りに興じた。
もちろん、熱々でボリューミーなオムレツサンドは、とびきり美味しかった。オリーブオイルのアクセントも、絶妙だ。
このカフェは、誰にとっても居心地のいい場所を作りたかったという彼女の理想そのものだった。
だが、いつまでもここにいるわけにはいかなかった。
「またね。らぶてあさん。いい旅を」
「Tさんも。ありがとう」
それから、商店街にある黒板とベンチに向かった。この黒板は、商店街の隠れたマスコットだった。
見かけるたびに、商店街の有志がチョークでオリジナルのイラストとメッセージを書き込んでいて、それがまたパンチの効いたものばかりで、並々ならぬ存在感を発揮していた。
また、アニメ好きならピンと来るキャラクターのセレクトばかりで、そこがまたユニークだった。

わたしは、黒板を背にした格好でベンチに座って、「絶望図書館」のページを開いた。
銀色に輝くベンチには、座布団代わりに緑色のタオルが敷かれていた。通りを行き交う人々のお喋りも足音も、心地良いBGMにぴったりだった。
そして、最初に収録されている短編を読み始めた。
佐々木マキという絵本作家がいる。
彼のイラストには、チャーミングで愛くるしい魅力がある。
だが、その魅力に三田村信行という児童作家の文章が加われば、たちまちブラックで無慈悲な恐怖に転じてしまう。
それを証明しているのが、「おとうさんがいっぱい」という短編だ。
ある日、ぼくのおとうさん「トシマ・タツオ」が三人に増えた。
ぼくはたったひとりで、おとうさんを一人に選ばなければいけなくなった……。
佐々木マキのシャープなイラストに、三田村信行の読みやすくて無駄のない文体がほどよくマッチして、最後までクイクイと読ませてくれる。
短編ということもあって、あっという間に読み終わる。
だが、その結末はあまりにも奇妙で、不条理なモダン・ホラーとしても魅力的である。
ホラーじゃないふりをして、素直じゃないものだから、最後の最後に牙を剥いてくる。
そんな、サプライズな読書体験をさせてくれる。
それに、二十年以上も前の短編だけれど、古さを感じない。
わたしにとっては、「誰もが旅人になる可能性」を告げているようだった。
ある日、自分が旅人としてあちこちをさすらうことになる。そんな恐ろしさを、自然と感じ取っていた。
かつて住んでいた町を旅して、そこでこの短編を読むという不思議さが、足をすくませた。
それでも、旅することは、止めない。
商店街のアーケードの下で、ひとり児童文学を読む。なるべくダークなやつを。
自分が、何を恐れているのかを学ぶために。
なぜ、旅をするのかを知るために。
ここから、どこに行くべきかを考えるために。
今日。
わたしはここで本を読む。
最新記事 by らぶてあ (全て見る)
- 読書空間 page05 「オメラスから歩み去る人々× 高台寺公園」 - 2018年4月19日
- 読書空間 page04 「非道に生きる× 桜井公園」 - 2018年3月15日
- 読書空間 page03 「おとうさんがいっぱい× 桝形商店街」 - 2018年2月21日